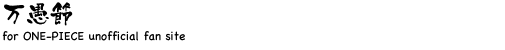01
盲目の釣瓶火
01
澄み渡る秋島の空に羊雲が浮かんでいる。涼風が通り抜けざま甲板の芝生を撫でていく。やわらかな陽射しが暖かい。
ゾロは腹巻きの中に手を入れると、大きく口を開けて欠伸を1つした。
着岸2日目、仲間達は今日も朝のうちから船を飛び出し、探索に余念がない。
アクアリウムバーのテーブルにはバスケットが置いてあり、中にはサンドイッチとメモが入っていた。少し堅い筆跡はコックのものだ。
文面は、惰眠を貪っていた剣士への文句が8割、バスケットの中身についてが1割、仲間達のスケジュールについてが1割で、ゾロはそれをしかめっ面で読んだ。
壁のリカーセラーから適当に2、3本抜き取り、バスケットを抱えて芝生甲板へ出る。天気がよいので外で食べようと考えたのだ。
マストにつけられた椅子へ腰掛けたところで、誰かが梯子を上がってくる気配がした。
ボトルの口を歯でこじ開けながら、見るともなしに見ていると、まず紙袋が手すりを乗り越え、次いで白いテンガロンハットが顔をのぞかせた。
「よう、随分と早い帰りだな」
「剣士さん……ただいま」
「おぅ、お帰り」
ロビンは風に遊ばれる髪を耳へ掛けながら、足元の紙袋を抱えると、ゾロへと歩み寄った。そうして彼の手元を見て小さく笑うと、
「それは朝ご飯かしら? それともお昼?」
「……今、何時だ?」
「1時よ」
「じゃあ、昼、だな」
ロビンは、きまり悪げにボトルを傾けたゾロをもう一度笑って、彼と向かい合うように芝生へ腰を下ろした。紙袋から、ふた周りも小さな袋を出す。
「私もこれからお昼なの。ご一緒しても?」
「構わねえよ。つか、仲間なんだから一々聞く必要ねぇだろ」
「そうね……ふふ、ごめんなさい。まだ昔の癖が消えないみたい」
そう言って笑うロビンを、ゾロは眉間に皺を寄せて一度だけ睨んだ。彼女に未開封の瓶を1本渡すと、無言でサンドイッチにかぶりつく。
手渡された瓶を見つめ、グラスがないことを確認して、ロビンは溜め息をついた。リュックから小さなナイフを取り出し瓶を開ける。口をつけてすぐに、
「あなた、ラベルも見ずに取ってきたわね」
「どうした、強すぎたか?」
「逆よ。思ったよりも甘くて驚いたわ」
「へぇ、俺のは普通だがな」
困ったように笑うロビンに、ゾロは片眉だけ上げて素っ気ない返事をした。ロビンは口を開きかけて何か言いたそうにしたが、黙って紙袋から買い込んだ昼食を取り出して食べ始めた。
「なんだ、お前もパンかよ」
「ベーグルサンドよ。本屋の向かいにあったの。美味しそうに見えたから、つい」
「1個で足りるのか」
「十分よ。いつもはルフィやあなた達と一緒だから、つい食べ過ぎてしまうだけ」
「……あれで食べ過ぎなのかよ。少しはナミを見習って食ったらどうだ」
ゾロは思い出すように視線を宙に浮かせると、呆れ声で言った。
「ナミちゃんはまだ育ち盛りよ。私とは違うわ。それに……気兼ねなく、心から美味しい食事ができるだけで幸せだもの」
ロビンが少し瞼を伏せてベーグルに口をつけるのを見ていたゾロは、自分の手にしたのが最後の1つだと気づいて、ふいに食べるのを止めた。ロビンの口元で少しずつ小さくなっていくベーグルをじっと見て、手のひらのサンドイッチに視線を落とす。
ロビンが半分ほど食べたのを見計らって、
「なあ、それ、食わしてくんねぇか」
「え……これ?」
「それだ」
「ごめんなさい、1つしか買ってこなかったの。また出かけるから、お土産に」
「今、食いてぇんだ。代わりにこっちをやる」
問答無用とばかりにサンドイッチを突き出したゾロに、ロビンは困惑した。再度、断ろうとしたがゾロの頑とした瞳に気づいて諦め、仕方なく食べかけを差し出す。
ゾロはロビンの手から素早くベーグルを取ると、空いた片手で引っ込みかけた彼女の手首を掴み、サンドイッチを握らせた。
ベーグルよりもずっしりと重いサンドイッチを前に、ロビンは向かいで自分の食べかけを口にしようとする男にぼんやりと視線を向け、その途端、顔を赤くした。
「待って。あなた、何して……」
「匂いも味も甘ぇ。お前、結構かわいいとこあんだな」
ベーグルの噛み痕に、微かだがロビンの口紅が付いていた。ゾロはそこへ鼻先をくっつけたかと思うと、舌を伸ばして舐めとったのだ。そうして羞恥に頬を染めるロビンに、にやりと笑いかけ何食わぬ顔でベーグルを食べだした。
まるで悪戯が成功した子どものような仕草に、ロビンは文句を言うタイミングを逃してしまう。思わず眉間をキュッと寄せて、少し乱暴にサンドイッチに噛みついた。
生成り色にトーストされたパンに、白身魚の見た目を裏切って、食感は脂身を削いだ豚のような肉が挟んである。トマトの甘味と、グレービーソースに柑橘類の酸味がアクセントになって、ボリュームはあるのにさっぱりした後味だ。
「美味しい。フィッシュサンドかと思ったけど、これは海獣の肉ね」
ワインで喉を潤しながら頬を弛めるロビンに、ゾロは指についたパン屑を払いながら、
「コックにゃ負けるが、このパンも美味ぇな」
「ねえ、いつも思うのだけど、その感想をたまには本人の前で言ってみてはどうかしら」
「ごめんだね。あのマユゲ、絶対つけあがる」
心底嫌そうに喉を唸らせてゾロは言った。その答えにロビンは、彼女にしては珍しく声を上げて笑った。楽しいことを見つけた少女のように。
目を見開いて凝視するゾロに気づき、ロビンはようやく笑うのを止めた。目尻に浮かんだ涙を指で拭いながら、
「ふふ、ごめんなさい。夕べダイニングでコックさんから全く同じ台詞を聞いたから、可笑しくて、つい」
「夕べ、って……アイツと飲んでたのか?」
「ごめんなさい、気を悪くした?」
「いいから、教えろ。アイツと二人きりで飲んだのか?」
急に機嫌の悪くなったゾロに戸惑いながら、ロビンは肯定の頷きを返した。
「そうよ……もしかして、彼、昨日はあなたと飲む約束をしていたの?」
するとゾロは足音荒くロビンの目の前まで来ると、彼女の顎をすくい上げた。戸惑いで揺れる漆黒の瞳を覗き込み、
「いつ言おうかと考えてたんだがな、この際だ……俺はお前に惚れている」
苛立ちを滲ませた声で告げた。
ロビンは黙ってゾロを見返していたが、瞼をそっと伏せた。そこへゾロが顔を寄せた時、顎を捉えていた指が下からはねのけられる。思いのほか強い力に眉をひそめたゾロだが今度は頬を叩かれ、二歩、後ずさった。
「何しやがる」
「それはこちらの台詞よ。大人をからかうものではないわ」
「からかっちゃいねぇ」
「そう。なら、なおのこと質が悪いわね」
頬をさすりつつ睨むゾロを負けじと睨んで、ロビンは淡々と告げた。
「この際だから言っておくわ。私はこの船の仲間を愛しているの」
「ならいいじゃねぇか」
「いいえ。だから誰か1人を特別に好きになることはないわ」
ロビンの言葉に、ゾロは顔を歪ませた。
02
盲目の釣瓶火
02
ロビンは、彼女にしてはやや乱雑にサンドイッチを食べきるとワインで喉を潤した。
その間、ゾロは眉間を寄せたまま、彼女を見ていた。
「愛しているのに、好きにはならねぇ?」
「そうよ。私は、私を光へ導いてくれたルフィと、あなた達みんなを愛しているわ。二度となくしたくはないの。だから、この船で特別は作らない」
「なぜだ」
「人の心は移ろうものよ。まして恋愛ならなおのこと。相思相愛の最中ならともかく、一度こじれてしまえば船全体がおかしくなる……そんな事態はごめんだわ」
「待てよ。なんで話がこじれる前提なんだ」
腕を組み、首を傾げるゾロにロビンは微笑を浮かべた。
「言ったでしょう。気持ちは変わるものだと。仲間のままなら、あなた達を裏切らない限り、私はこの心地よい場所にいられるわ」
ロビンの言い分に一理あるのも確かで、彼女のどこまでも柔らかな拒絶に、ゾロは返す言葉を探し倦ねた。だが、ふと単純にして重要なことに気づく。
「……つまりお前は、端っから俺が心変わりをすると決めつけているわけだな?」
「違うとでも言いたそうね。敵だった人間を、好きだと告げること自体、大きな心変わりではなくて?」
「ビビとのことなら、そもそもお前は敵とは言いがたいだろう」
ゾロの言葉にロビンは声を上げて笑った。
「ますます可笑しな人ね。この船で誰よりも私を信じていなかったあなたが、なぜそう言い切れるのかわからないわ」
「あん時はな。だがルフィがお前に助けられたと言った時点で、俺はお前を受け入れてはいたぜ。信じられなかったのは、お前が本心を隠していたからだ」
ロビンの表情が変わる。
ゾロはそれを見逃さなかった。大股で歩み寄り、彼女と真正面に向き合い腰を落とす。勢いに驚いて退くロビンを、芝生に両手をついて追いかける様は、獲物を追い詰める獣に見えなくもない。
船縁へ背を打ちつけられて逃げ場を失ったことに気づいたロビンは、はじめてゾロに怯えに似た視線を寄越してきた。彼女の瞳をゾロは笑って流すと、船縁に手をついてロビンを閉じ込めた。揺れる黒髪をかきあげて耳元に口寄せる。
「お前が好きだ」
吐息に重ねて囁かれた言葉に、ふるりと身を震わせたロビンの首筋に、ゾロは鼻先を擦り付け、
「好きだ」
再び囁いた。
密やかに告げられる懇願にも似た声音に、ロビンは、はね除けるタイミングを計り損ねてしまう。緑の髪が首から胸へと移動し、胸の相中、心臓の真上あたりで止まった。ゾロの唇が軽く押し当てられ、思わず身体が跳ねる。
「好きだ」
布地を通して、熱い吐息が侵入する。ロビンは動けなかった。彼の想いにやんわりと閉じ込められるような錯覚に陥りそうになる。
「ロビン……好きだ」
「やめて!」
それは、今まで一番激しい拒絶だった。
ハナハナの能力を使い、腕を余分に生やして全力でゾロを突き飛ばす。
油断もあったのだろう、さすがのゾロもこれは防ぐことが出来ずに顔から芝生へ滑り落ち、甲板を半分程転がってしまった。
「剣士さんっ」
驚いたロビンの声が甲板に響く。
「……平気だ。ちっとビビったがな」
「ごめんなさい……でもお願い、これ以上はやめ」
「断る」
ゾロは地面に打ちつけた頬を撫でながら起き上がったが、指の腹が僅かに違和感を捉えた。指先を見ると、赤い線が走っている。ロビンに視線を戻してみると、両手をぎゅっと握りしめていた。
「お前、手ェ大丈夫か」
「え?」
ゾロの言葉にロビンは言われるがまま自分の手を見た。形よく切り揃えられた人差指の爪先に、赤い色が付いている。男の顔に薄い朱線が浮んでいる。意図せずにゾロを傷つけたと気づいて、ロビンは動揺した。
「ごめんなさい」
「ワザとじゃねえんだから謝るな。それより、逃げるな」
「な、」
「俺から、逃げるな」
「言ったでしょう、私は」
「聞いた。けどお前のソレは本心じゃないだろう。だから、俺は諦めねぇ」
「無駄よ」
「無駄かどうかは俺が決める。いいか、俺は絶対にお前を引きずり出してやる」
「あなたの心は変わろうとも、私の決心は変わらないわ」
「どうかな……人の心は移ろうもんなんだろう? 生憎、俺はお前を嫌いになる自信がねぇんでな。なら、お前の心を変えてみせる」
「私なんかより、ナミちゃんや、それにもっと素敵な人が現われてくるでしょう」
「そうやって、いつまで引っ込んでいる気だ。一人でいるのは止めたんだろう。なら四の五の言わずに、もっと素直になれよ」
いつになく饒舌に語るゾロに、ロビンは不覚にも押されていた。ゾロの言葉が、彼の我侭であると気づいている。だが、それに反論する自分の言葉も我侭であることをロビンは知っていた。
なによりも、ゾロの力のこもった目線にすでに押され気味だった。自分を助けてくれたクルーを大事にしたい。だから、自分のために傷つく姿をこれ以上見たくはなかった。たとえば、それが恋愛という甘やかな感情を伴うことであっても。
「……素直になれなくて結構よ」
溜息とともに、吐き出された言葉は、彼女自身でも驚くほど酷く弱々しく聞こえた。
03
盲目の釣瓶火
03
俯いたロビンを前に、ゾロは肩を軽く鳴らして、指に付いた血を舐めた。空を仰ぐと、陽は傾きを深くしている。そろそろ誰か戻ってくる時分だろうか。
「お前が俺たちを欺いた時、正直に言うと腑が煮えくり返りそうだった。俺たちが想うほど、お前には想われていなかったと思ってな」
綿雲の群れを見つめたまま、独り言のように呟いたゾロの言葉にロビンの顔が大きく歪んだ。
ゾロは自嘲を込めた笑みを浮かべて視線を雲からロビンに移すと、静かに彼女へと近づいた。ゾロを見上げる黒曜石の瞳が薄く濡れて見えている。
壊れものを包み込むように頬に触れてきた武骨な手のひらに、とっさに瞼を伏せたロビンの耳へ、ゾロの揺れる声が届いた。
「お前の真意をナミから聞かされた時、後悔した。迷わずに、とっとと捕まえて抱いておけばよかったと」
頬に添えられた手は暖かく、ゾロの気持ちそのもののように感じられた。ロビンの目尻の縁を親指がなぞり、溢れ出した涙を拭っていく。
「なぁ……ずっとこの船にいる気なら、俺を好きになれよ」
温もりが離れたのもつかの間、今度は指の背で頬を撫でられる。静かに侵食してくるゾロの熱がロビンの喉奥を焼いてひりつかせた。
「ごめんなさい、できないわ」
「……俺以外の誰かが好きなのか?」
ゾロの、ひどく掠れた声で発せられた言葉は、考えてもみなかったものだったので、ロビンは思わず目を開けて彼を見つめた。
「……いいえ。言ったでしょう。私はあなた達と特別は作らない」
「ルフィが……もしも、あいつが望んだとしたら?」
「同じことよ。それに、彼はもう、特別を手に入れているでしょう」
「そうだな」
ゾロの指は相変わらずロビンの頬を行き来している。
どうしてよいか分からなくなったロビンは、とりあえずゾロから離れようと、自分に触れている手を掴もうとした。すると逆にその手に捕らえられてしまう。
眼前に持ち上げられた手は、男の手にすっぽりと覆われていた。
陽光を背負った剣士の、左耳を飾るピアスが光を弾いてロビンの瞳を射る。狭まれた視界に、男の軽やかな笑顔が映り、鼓動が跳ねた。
ゾロは手の中にあるロビンの人差し指へと口寄せた。そこにはゾロの血が薄く乾いて張りついている。
「あ……」
指先を生暖かい熱に包まれて声を出したロビンを、ゾロは目を細め無言のまま見返しながら丁寧に己の血をぬぐい取っていった。
名残を惜しむかのように爪先に口付けを落として顔を上げたゾロの目に、頬を上気させたロビンの潤んだ眼差しが映る。
「お前が俺をも愛しているというのなら、俺はお前の特別になってみせる。必ずな」
ゾロは、いつもの不敵な笑みを口端に乗せ、ロビンの鼻先すれすれまで顔を寄せて宣言すると、彼女の唇に自身を重ね合わせた。
艶やかで柔らかい女の唇に残っていた紅をゾロの舌がなぞり、ぬぐい取っていると、ロビンが身じろぐ気配を感じて、素早く身を起こし飛び退く。
口元を覆い固まっているロビンに白い歯を見せてゾロが笑った。
「今のうちに覚悟しておけよ。さっきも言ったと思うが、俺は絶対に諦めねぇから」
言ってすっきりしたのか、ゾロはロビンの返事を聞かずに彼女に背を向けると、甲板に転がっていた空き瓶を拾いだした。
我に返ったロビンが赤い顔のまま立ち上がったのと、ゾロが彼女の方に振り返ったのは偶然だ。
しかしゾロは、ロビンの瞳に、今までとは違う感情を確かに見つけた。
「剣士さん、」
「ただいま! ゾロ、梯子を下ろしてちょうだい!」
ロビンの言葉は、陸からかけられてきたナミの声で途切れてしまい、彼女がなにを言おうとしたのか分からなくなった。
ゾロは、船縁へと向かいがてら芝生に転がっていたテンガロンハットを手に取ると、風に揺れる黒髪にそっと被せた。そうして何事もなかったかのように船の外へ身を乗り出し、ナミの姿を確認すると梯子を下ろし始めた。
ゾロがナミを手伝っている間に、ロビンは自分の荷物を抱えて女部屋へ駆け込んだ。ソファに荷物を置いて、部屋に備え付けられた洗面台の鏡を覗く。
そこには頬を薔薇色に染めて今にも泣きそうな少女が映っていた。
「……ダメよ、ロビン。これ以上望んでは、また以前のように彼らを……あの人を失うことになるのかもしれないのだから。求め過ぎてはいけない、期待し過ぎてもいけない……人の心は移ろうものだから」
自分自身の姿を少女のようだと思うことに可笑しさを抱きながら、ロビンは鏡に向かって言い聞かせるように呟いた。
ロビンの言葉に鏡の中の少女は一瞬、痛みをこらえるように眉を寄せたが、すぐに小さく首を縦に振った。
それからロビンはソファの荷物を自分のベッドに移すと、気持ちを切り替えるために軽く顔を洗った。冷たさをはらむ水が、強張っていた神経をほぐしすっきりさせていく。
夕飯まで、まだ時間がある。もう一度、町へ降りても十分間に合うはずだ。
「しばらくは、彼と距離を置いた方がいいでしょうね。曖昧な態度では、彼に過剰な気持ちを抱かせてしまうから」
リュックを手にしつつ、ロビンはそう独りごちて、女部屋のドアを開けた。
04
盲目の釣瓶火
04
女部屋から出てきたロビンにナミが気づいて手を振る。
「ロビン! 帰ってたんだ」
「おかえりなさい、ナミ」
「ただいま。んもう、お昼一緒に食べようと思って街中探してもいないわけだわ」
ナミの足下には大小幾つもの袋が置かれており、上機嫌な彼女の様子から満足のいく収穫があったということが見て取れた。
ロビンはリュックを肩に掛けながら、ナミの傍らに立つゾロにはなるべく視線を向けず、彼女に近づいた。
「それは悪いことしたわ。荷物がかさばって少し邪魔になってきたから置きにきたの。ごめんなさいね」
「ま、いいけど。アタシ達はみんなでお昼を食べたけど、ロビンはちゃんと食べた? 前みたいに本屋で夢中になって食べてない、とかじゃないわよね?」
両手を腰にあてて、ロビンに問いかけるナミを見ていると、どちらが年上なのだかわからない。
過去の所行を指摘されて、ロビンはほんの少しだけ苦笑いを浮かべてしまう。そうしてきちんと昼食をとったと伝えようとしたその時、思いもよらず横合いからゾロが割って入り、ロビンはつい、口をつぐんでしまった。
「その心配はねぇ。町で買ってきたとかで、ドーナツみてぇなサンドイッチを俺と一緒に食ったから」
「ふうん、そうなんだ」
訝しむナミを気にしたふうもなく、ゾロはロビンを真正面から見ながら淡々と言葉を繋いだ。
「お前、本屋に行くつもりなんだろ。早くしねぇとみんなが戻ってくるぞ。そうなったら出かけにくくなるだろ」
「そうだけど、あの」
「なら、今のうちに行ってこいよ。晩飯に遅れそうなら俺からコックに伝えておく」
ゾロの、早く行けと言わんばかりの気配に押されて、ロビンは落ち着かないままに船を降りた。2人の間を通り抜けた際に、ナミの意味ありげな視線を受けて益々気がそぞろになる。船に残った彼らが一体どんな会話を交わしているのか、いつもは気にもとめないことが、小さな棘のように心に引っかかった。
船の上では、小さくなるロビンの後ろ姿を見送っていた2人が無言で突っ立っていたが、そのうちゾロの方が焦れて口火をきってきた。
「ナミ、この島のログが溜まるのにどれぐらいかかる?」
「後3日はかかるわ。ゾロ」
「なんだ」
「ロビンを泣かしたら、アタシが許さないんだから。アンタ覚悟できてんでしょうね?」
存外に、ロビンとの仲を指摘されてゾロは思わずナミの横顔を凝視した。
潮風に混じってオレンジ色の髪から、同じ名を持つ果実の香りが漂い、ゾロの鼻を擽る。
ナミはゾロの気配を左頬で感じとりながら、ロビンから目をそらさずにいた。
「でなきゃ告ったりしねぇよ。それに……ついさっき振られた」
「え?」
—2度も言わせる気かよ。
ゾロはそう思いながらも、頭を掻きつつもう一度繰り返した。
「だから、あの女に振られたんだよ」
大きなため息に乗せて吐き出された男の言葉は、ひどく頼りないもので、ナミは知らず、手すりに乗せた腕に力を込めた。
「ウソ」
零さんばかりに目を見開いて、ゾロを見る。その様子に引っかかるものを感じて、ゾロは片眉を跳ね上げた。
「なんだよ?」
「だって、ロビンが好きなのゾロだもん」
「は?」
「だからっ、ロビンはアンタが好きなの」
「……マジ、かよ」
にわかには信じられないその言葉に、刀の柄尻を強く握りしめて気を散らした。
ナミは頬杖をついて、もう見えなくなったロビンの背中を思い出しながら、
「ゾロ、まさかと思うけど、ロビンにまずい言い方したんじゃないの」
「お前、俺を何だと思ってんだ」
「ファンタジスタマリモ」
あっけらかんと返された答えに、ゾロはつい青筋を立ててしまう。だがここで不必要に喚いてもどうにもならないので、深呼吸をしてごまかした。
「好きだ。それだけ告げた」
「そう」
「……何か言いたそうだな」
「アンタにしては上出来じゃない。なのになんでロビンは断ったのよ」
風に遊ぶ髪を耳に掛けながらナミは語尾を強くした。
「特別は作りたくないんだとよ」
「なによ、それ」
不信感を隠そうともせず睨みつけてくるナミに、ゾロはぽつぽつと先程の出来事を語りはじめた。
事情を聞き終えると、ナミは可愛らしく首を傾けて、口をつぐんでしまった剣士に笑いかけ、
「それで、振られた剣豪さんは今夜は失恋のやけ酒でもするのかしら」
「誰が諦めるって言ったよ」
「なに、リベンジ?」
「当たり前だ。大体、アイツの言い訳なんざ納得できるか」
「なんだ、そこは気づいているんだ」
「ナミ……お前、本気で俺を何だと思ってんだ」
「迷子のマリモ」
「テメェなぁッ」
「冗談よ。……少し見直したわ」
話しは済んだと足下の荷物を手にして、ゾロの肩を軽く叩く。
数センチ下から見上げる力強い瞳を、ゾロは黙って受け止めた。
「ゾロ、もっとちゃんとアンタの言葉でアンタの気持ちをロビンに伝えて」
「ナミ?」
「仲間を信じることと、誰かに心を預けることは違うのよ……特に女の子はね」
「どういう意味だ」
「アタシは、この船のみんなを信じているけど、ルフィに預けている気持ちはそれとは別のものだってこと」
わかる? そう無言で問いかけられる。
「……つまり、つまらない考えなんざ抱かないくらい、アイツを、ロビンを捕まえておけばいいってことか」
「極論ね。当たってはいるけど」
やれやれと肩をすくめたナミへ、ゾロは渋い顔を見せる。
「大体、そんな言葉遊びならクソコックかウソップとやれよ」
「イヤ。アンタとだから楽しいんじゃない」
彼女は舌をぺろっと出しておどけてみせた。
「さてと、荷物置いてくるからお茶にしましょう。ゾロ、先にダイニングでお湯を沸かしておいてちょうだい」
「俺がかよっ」
「だって、アンタの恋愛相談に乗ってあげたんだもの。当然でしょ」
ひらひらと手を振って女部屋へ消えたナミの背中へ、ゾロは思い切り舌を出して見送るとキッチンへの階段を上がった。
05
盲目の釣瓶火
05
島の南東に位置する街の大通り。この通りと並行して、ひと回り小さな通りがほぼ真っ直ぐ東西に走っている。通りの端から端まで、徒歩20分程度という長さだ。
石畳で舗装された地面には赤や緑に彩られたテントが軒を連ね、ワゴンの上では様々な食材が山と積まれている。島中のほとんどの産物が集まる市場だ。
呼び込みの声を背中で聞き流しながら、サンジはとあるワゴンの前でお喋りに花を咲かせていた。店主は商品に負けないくらい赤い髪を頭上で団子に纏めた大柄な中年女性で、今にも弾みそうな丸い体を揺すりつつ、大声でサンジと話している。
果樹園の香りを留めている、見た目がリンゴによく似た果実を吟味していたサンジは、視界の端をよぎった女性に心を奪われた。
慌てて振り返ってみると、なめらかな黒髪を肩先で切り揃え、身に着けたワンピースは美事な体躯を際立たせる仕様だ。色を滲ませながらも、静謐さに包まれた佇まいは近寄りがたい雰囲気さえある。控え目にひかれた口紅も、とてもよく彼女に似合っていた。
周りの出店に興味が無いのか、あるいは別に目的地があるのか、彼女はただ真っ直ぐに前を向いてサンジの側を通り過ぎていく。
「ロビンちゃん!」
サンジは思わず彼女を呼び止めた。
振り向いたロビンは、一瞬呆けたような表情を見せたが、すぐにいつもの澄んだ微笑でサンジに近づいてきた。
「コックさんは、まだ買い出し中なの?」
「ご名答、吟味中でね。今はこちらのマダムから果物が安く手に入らないか交渉中ってところかな」
おどけた調子でサンジはワゴンの女店主に右目を瞑ってみせた。左目は相変わらず金髪の下なので、そうすると涼しい表情からやんちゃな少年の気配が顔をのぞかせる。
妙齢の女主人はワゴンの山から食べごろの実を2つ選び取ると、ロビンを手招いた。不思議そうに小首を傾け近寄る彼女の手に、その実を乗せて大きな胸を揺らして笑いかけた。
「サービスだよ、持っていきな」
「え……」
「もらっときなよ、ロビンちゃん。味見だと思ってさ」
「そうそう、女の子が遠慮しちゃいけないよ」
「そうそう、遠慮するのはウチのクソザルだけでいいんだから」
「サルねぇ、ひょっとしてさっきまで一緒にいた子のことかい」
「その通り。胃袋が海王類並みなサルさ。ああみえてもウチの船長なんだ」
「とてもそうは見えなかったけどねぇ。そうかい。ホッホッホ、兄さんの料理を腹一杯食べられるなんて幸せもんだよ」
「ははは。やだなぁ、マダム。さっきの約束はちゃんと守るよ。まだ少し滞在しているから」
サンジは女主人と会話を楽しみながらも、2人を交互に見て戸惑っているロビンの手から実を1つ取り上げ、服の裾で軽く拭いた。
ロビンはサンジの手を見つつ、
「約束?」
と聞いてみた。サンジはちら、とロビンを見返すとワゴンに顔を向けて、
「コイツを安くで譲ってもらう代わりに、マダムへお返しの一品をご馳走するって話をしてたのさ」
どこから出したのか小さなナイフを手にすると、手際よく皮を剥いていく。食べやすい大きさに切り分けた後、ロビンの手を汚さぬように、皮の一部を実に巻き付かせた。
「どうぞ、レディ。完熟の恵みを召し上がれ」
優雅に差し出された一切れは、みずみずしさに溢れている。ロビンは女主人に会釈をして、サンジが手にしたままの果実を直に口にした。
「ロビンちゃん!?」
ひっくり返った声で小さな悲鳴を上げたサンジに視線だけで応えて、ロビンはもう一口齧る。
梨の様な食感と、桃に似た濃厚な甘さが口の中に広がる。喉を通る果汁は甘さに反して爽やかで、ロビンは、随分と自分が乾いていたことに気づいた。
「ごちそうさま。とても美味しかったわ」
美味なる恵みに、うっとりとして感想を述べた。
「お嬢ちゃん、あたしゃ遠慮はするなとは言ったけどね」
女主人が苦笑いでサンジへ顎をしゃくる。かわいそうに、白磁の肌を朱色に染めて、サンジは硬直していた。
「口説き文句はいっぱしだけど、女の子に慣れてないみたいだね」
「ふふっ。彼、騎士道の固まりなの。素敵でしょう?」
「やれやれ……あたしゃ、あんた達を気に入ったから言うけどね。見たところ、お嬢ちゃんは兄さんの仲間らしいけど」
「ええ、そうよ」
「なら、あたしのお節介を聞いときな。お嬢ちゃんのような若いコが、あんまり兄さんみたいなのをからかっちゃいけないよ」
女主人は、少し改まった声でロビンに話しかけてきた。情を滲ませた彼女の姿勢に、ロビンも口元の笑みをしまって彼女と向き合う。我に返ったサンジが何かを言う前に、女主人は肉厚な手のひらを向けて彼の口を制した。
「あたしゃ、詳しくは知らないが、お前さん達の絆は随分しっかりしたものだね」
頷いたロビンに、口調を幾分柔らかくして、女主人は言葉を続ける。
「船旅は余計な気遣いを煩わしく思うところも多いと聞いているよ。けど、あんた達の船はそうじゃないとみた」
どうだい?──視線で問われたのはサンジで、彼はくわえたタバコを上下に揺らし肯定のサインを送った。
「老婆心だよ。お嬢ちゃん、自分に素直になれないうちは仲間に甘えちゃいけないよ」
「マダム、そうじゃないだ。彼女は……」
「今は、そうだろう? 兄さんも、いつまでもお嬢ちゃんを甘やかしてちゃいけないね。ちゃんと叱ってやらにゃ」
女主人はやんわりと目を細くしてロビンとサンジを試すように見た。
「できるかい?」
「努力するよ。いいや、できる」
即答したのはサンジ。
ロビンは、我慢する子どもみたいに小さく、掠れ声で、
「無理よ。だって、どうすればいいのか、わからない」
「自分にもっとわがままになることだね。そうすりゃ、人の好意も素直に受けとめられるようになるよ」
女主人がワゴンの奥から身を乗り出してきた。俯くロビンの頭を撫でる彼女の手は、母親のように温かく慈愛に満ちていた。
06
盲目の釣瓶火
06
サンジは沈んでしまったロビンの腕から、静かにリュックを取り上げると自分の肩に担いだ。女主人と二言三言、言葉を交わして彼女から書付を受け取り、そのまま彼女に暇乞いのあいさつをすると、ロビンの手を握り市場を後にした。
無言のまま連れられるロビンを時折振り返りながら気にしつつ、サンジは足を繁華街へと向ける。
頭上を仰げば傾きを深くした日差しが柔らかく降り注ぎ、風が街路樹の間を吹き抜ける度、ちらちらと黄色や朱色に染まった葉が舞い落ちていった。空気が、冷たさをはらんでいる。
繁華街を貫く大通りは四輪馬車が楽にすれ違うことの出来る幅があり、様々な店が並んでとても賑やかだ。
サンジはテラスを大きく構えたカフェに腰を落ち着けることにした。テラス席でも日当たりのよい、店の入口からは一番奥まったテーブルを選ぶと、目隠し代わりの植え込みが側にある椅子をロビンに勧めて自分も隣りに腰掛けた。
物腰の丁寧なギャルソンの接客に気をよくしつつ、アイリッシュコーヒーと、ロビンにはアーモンド・ラテをそれぞれ注文する。それからテーブルに備え付けの灰皿を手元に引き寄せ、一服つけはじめた。
入店の際、素早く店内の様子を探ってみたが、こ洒落た雰囲気を重視しているのだろう、無粋な手配書の類は見あたらなかった。客の中にも、こちらが注意を払う人物はいなさそうである。
「ごめんね、ロビンちゃん。用事があったんでしょ?」
「いいえ、時間があるなら午前中に立ち寄った本屋にもう一度、と思っていたぐらいだから気にしないで」
「そうなんだ。なら、もうしばらく俺に付き合ってもらっても?」
「私は構わないけれど……コックさんのほうこそまだ予定があったのではなくて?」
ロビンの言葉を聞いて、サンジは椅子から身を起こして彼女に顔を近づいた。
「レディの抱えた悩み事に比べたら、俺の用事なんてカームベルトの彼方さ。ま、もっとも今日の予定はさっきのマダムで終わりなんだけど」
「悩み、って」
「ゾロとなにかあった?」
「どうして……」
驚くロビンに答えず、サンジは再び椅子に身を沈めた。そこへギャルソンが静かにトレイを掲げてテーブル脇に立ち、注文の品ができたことを告げる。
サンジは両手を絡め、ゆっくりとした動きで足を組み替えた。隻眼を眩しそうに細め、落とした声音で、
「アーモンド・ラテを彼女に」
とだけ応える。
ギャルソンは軽く目礼すると流れるような動作でセッティングを済ませて去っていった。カウンターへ下がる背中を見送ったサンジがロビンへ視線を戻し、
「冷めないうちに先ずは心を温めて、ロビンちゃん」
ラテを勧め、気取った口調で微笑んだ。
サンジは時々、こうして意図的に紳士を演じることがある。それは、クルーの誰かが悩み事を1人で抱えている時だ。たとえ他愛のないものだろうと、サンジは抱え込んでいることをよしとしない。もっとも、サンジ自身は抱え込んで隠し通すので、厄介だったりするのだが。
サンジは自分の手元のカップに視線を落とし、スプーンの上でアルコールに身を焦がす砂糖の青白い炎を見つめながら、
「種明かしをしようか。ロビンちゃんが俺の後ろを通っただろ。あの市場はね、他の通りへ抜け出る道が限られているんだ。横道は全て一方通行でね、ロビンちゃんが来た道は海岸から通じている市場の入口、つまり一本道だ。俺は昼をナミさんやルフィ達と過ごした後、真っ直ぐ市場へ向かった。ロビンちゃんがあそこから来たということは、一度船に戻ったから。そして船番は寝腐れて置いてきぼりをくらったマリモがいるだけ」
「それだけでは、根拠にならないわ」
ロビンの鼻先でサンジは人差し指を横に振る。
「あるさ。常に注意を怠らない君が上の空で歩いていた。ロビンちゃんをよく観ている仲間なら、今述べた事実を照らして、貴女とヤツの間に何かあったと気づいてもおかしくないよ。それともう1つ」
「なに、かしら?」
「俺とナミさんは三日前、アイツが不寝番の時に君について相談をされたのさ」
どうだい?ーサンジは流れる水のごとく、自分の推理を語ると再び椅子に身を沈めた。
ロビンも知らず、張っていた肩の力を抜く。両手で包み込んだラテのカップから、緩やかに指先へ伝わる熱が体内に染みていくのを感じながら、
「時々、コックさんが怖くなるわ。気づき過ぎて」
「誉め言葉として受け取っておくよ。それじゃあ次は俺の質問に答えてくれるかな。どうしてロビンちゃんは俺とゾロだけ名前で呼んでくれないの?」
予想もしていなかった質問に、ロビンは今度こそ固まった。
「それは」
──どうしてだろう。
ロビンは答えられなかった。
「わからない?」
サンジはコーヒーカップを口へ運びながら、なおも問いかける。
「今だってそうだ。他のみんなは名前で呼ぶのに、俺とアイツだけ名を呼ばないのは、ロビンちゃんにとって俺達2人が特別だってことじゃないのかい」
「どういう意味かしら」
特別という言葉に込められた力に、思わずサンジを見る。
「そうだな……」
サンジはスプーンでコーヒーをかき混ぜ、
「例えば、アイツと俺を男として見ているとか、ね」
ロビンの肩が一瞬、確かに跳ね上がった。
「ロビンちゃんは自覚してないようだから、本当は言うべきではないんだけど。いい加減、あのマリモが煮詰まっているみたいだから、協力してやろうと思ったんだ」
サンジはそこで口元を隠し、声を抑えて笑った。視線が少し遠くを見ているのは、相談してきたゾロを思い出しているのだろう。
「ねぇ、ロビンちゃんは何をそんなに怯えてるのさ」
サンジの語りかけは相変わらず静かだ。質問を考えながら、不意にロビンは気づいた。彼が常日頃、女性にメロメロする姿をまだ見せていないことに。
「剣士さんのために、真面目に聞いているのね」
「もちろん。仲間の真剣な恋路を茶化すほど、俺は愚か者ではないよ」
サンジはきっぱりと答えた。
彼の言葉にロビンは再び沈黙した。短くなった煙草を灰皿に押しつけ、サンジは真っ直ぐに彼女を見る。常ならば優しさのみを湛えている隻眼が、底の見えない意思をはらんでロビンに迫ってくるようだ。
サンジの言葉を反芻しながらロビンは彼の言う、特別、について考えてみた。だが、答えを慎重に選んでいる思考の片隅で、先ほどから言い表せぬ警鐘が鳴り響いている。それは、ゾロに告白された時に感じた何かにとてもよく似ていた。
「そうね、貴方と彼は私の中では確かに特別だと思うわ。でもそれは、男性としてではないと思う」
「根拠は」
「貴方達は他の仲間と違って、私を本気で嫌いになりそうだからよ」
「なるほど正論だ」
サンジはロビンの答えに動じるどころか、愉快そうに笑った。それを受けてロビンはため息に乗せて自傷の笑みを唇に浮かべた。
「剣士さんもだけど、貴方は真に疑うことを知っている。そうでなければあの時、海列車に乗車できたはずがないわ」
「それは過大評価だ。俺はただ、レディは時に心にもないことを上手に言えることをジジイから教わっただけさ。それと……嘘つきから嘘を見抜く手ほどきを受けたぐらいかな」
そう言ってサンジはコーヒーを口にした。ロビンの目に、カップの向こう側に隠れたサンジの頬がほんのりと色づくのが映った。どうやら照れているらしい。
「貴方達は皆、どこまでも真っすぐだわ。私には時々それが眩しすぎるの」
俯いたロビンの手のひらにくるまれたラテは、遠い砂の大地を思いおこさせた。霞のごとく立ち昇る湯気は、自分だけを信じていた砂の化身のようだ。どこまでも横柄で野心家だったあの男は、泣いた仲間を助けるためだけに拳を上げた少年に負けた。そうして少年の海のように広大で灼熱をはらんだ意志はロビンをも生かした。掛け値なしで自分を求めてくれた、あの温かな手をロビンは二度と失いたくないと切望している。
「ロビンちゃんは嫌われるのが怖いんだね」
「貴方達にね」
「麦わらの一味に? 他はいいの?」
「世界を敵に回そうと、貴方達が側にいるなら生きられるわ」
「それは光栄」
サンジは胸に手を当て軽く上体を折り曲げた。身を起こしたサンジの瞳はなぜか悪戯を仕掛けるように煌めいていて、ロビンはついカップを握りしめてしまう。
「なら、俺から1つ、アドバイス」
「なにかしら」
警戒するロビンを笑い、サンジは続けた。
「まずはケンカしてみなよ、ゾロと。昼間の事を持ち出してさ。勝ち負けはどうだっていい。大丈夫だよ。ロビンちゃんのそれは杞憂だ」
「そう、なのかしら」
ロビンには、わからなかった。だがサンジは、カップをソーサーに戻して静かに言った。
「そうさ。ロビンちゃんのそれは大きな間違いだ。笑ってるだけじゃ駄目だよ。ケンカして仲直りして、そんなことを繰り返して俺達は仲間になるんだ」
人差し指でカップの縁をなぞりながらサンジは通りに目を向けている。
「俺はアイツとケンカばかりしているでしょ。でもアイツのことが嫌いなわけじゃない」
「ええ、知っているわ」
サンジとゾロのケンカなんて、日課のようなものだ。ロビンが麦わらの一味に加えてもらった日から、2人は絶えず諍いを起こしている。仲が悪いのかと思いきやそんなことはなく、単なる意思疎通のじゃれあいだと気づくまで日はかからなかった。
「あなた達のケンカが、ルフィとウソップの遊びと同質のものだと気づいた時には呆れたものだけど」
「ははっ。船は丈夫になったけど、小言と拳骨が増えたのは予想外だったかな」
サンジは悪戯が見つかった子どものように、肩をすくめておどけてみせた。相変わらず、ロビンを見ないまま、ジャケットの内ポケットからタバコの箱を取り出し、テーブルに置いた。
今度は吸わずに箱の表を指先で拍を刻むように叩いている。
07
盲目の釣瓶火
07
色白の細長い指先から規則正しく刻まれる音は時計の秒針に似ている。ロビンは黙って耳を傾けながら表通りへと視線を流した。
サニー号でゾロと交わした内容を思い出してみる。
ゾロの言葉に偽りはなかった。あの温もりを手にするのをためらったのは、真摯過ぎて怖いと思ったからだ。
「好意を恐れていちゃ、前には進めないよ」
「コックさん……私、ひょっとして口に出していた?」
「うん。ねぇロビンちゃん、1つ実験をしてみようか」
「何を実験するの」
「君自身も探している隠された本心が、ゾロの事をどう思っているのかを知りたくはないかい」
サンジは相変わらず、楽しそうな顔でロビンを見つめている。
深呼吸を一つして、ロビンは彼に向き合った。
「どうやって試すの?」
「まずは目を閉じて」
ロビンは言われるままに瞼を閉じた。
「君は今、誰といる?」
「貴方よ、コックさん」
「当たり。いいかい、決して目を開けちゃ駄目だよ。……そのコックさんが、例えばこんな風に君に触れたとしたら?」
するりと、サンジはロビンの手の甲を人差し指で撫でた。
──意思を込めて。
途端、ロビンの手は彼女の懐へ逃げるように引き戻された。
「コックさんっ」
「さあロビンちゃん、君は今、どんな気持ちになった?」
すかさず問われて、ロビンは眉根を寄せる。
「コックさんだと知っているから、驚いたけど嫌悪感はないわ。ただ剣士さんが触れた時とは違う感じ」
「ただ驚いただけ?」
「そう、ね……いいえ違うわ。貴方にずっと、そんな対応をされるのは本意じゃない」
視界を閉ざしたロビンにははっきりとわからないが、サンジが微笑んだ気配がした。
「俺が君に恋愛感情を抱くのは困るんだね。それは、君にその気がないからかい?」
サンジの指が再度ロビンに触れる。今度は含みのない、普段と同じ接触だったため、ロビンも振り払うことはしなかった。
「さて、俺が仲間としてこうして触れるのは構わないというロビンちゃんに次の実験ね。例えばこの手がゾロだとしたら、君はやっぱり何とも思わない?」
「え……」
「想像してみて。今、君に触れているのはサンジじゃない、ロロノア・ゾロだ」
サンジの声がぐっと低いものに変わる。
「よく思い出せ。俺がお前に触れた時の感覚を」
口調まで変わったサンジは、ゾロにとてもよく似ていて、ロビンは息をのんだ。
男に力を込めて握られた手のひらが、じっとりと汗ばんでくる。
瞼を通して入るほの白い日の光を見ながら、ロビンは昼間のゾロを思い浮かべてみた。
食べかけのベーグルに付いた口紅を舐めとっていた横顔を。自分以外の男性といたことに不機嫌になった瞬間を。唇を押し付けてきた時に伏せられた瞼の縁を。
好きだ、と告げてきた高炉のように燃えた瞳を。
「好きだ」
低い囁きを耳元で告げられて、ロビンは自分の体温が上がるのを感じた。同時に、身の内からくる震えを止めたくて男の手を握り返す。
ロビンの反応に驚いた彼は、すぐに落ち着かせるように彼女の両手を包み込んだ。
「俺のこと、嫌いじゃないんだな」
サンジの台詞は、まるで船での出来事を見ていたかのようだ。
「嫌いじゃないわ。ただ」
「ただ?」
「貴方に見つめられた時、落ち着かなかった」
「なぜだ」
問われた声にロビンは軽い目眩を覚えた。自分と一緒にいるのは本当に金髪の料理人なのだろうか。あまりにも剣士に似すぎている。
「故郷を亡くした時から……私は偽りの好意しか知らない」
「俺もそうだと言うのか」
「いいえ」
閉ざした視界でも、ロビンの答えに男が安堵したことがわかった。
それがなぜか嬉しくて、ロビンはほんの少しだけ、己の過去を吐露した。
「生きる為には何でもしたわ。……私は、悪意に慣れているけれど、貴方や仲間がくれる気持ちには慣れていないのよ。だから、どうしたらいいのかわからないの。さっきの屋台でもそう。あの人が頭を撫でてくれた時、私はどう返せば良かったのかしら」
「笑って、ありがとうって言えばいいと思うよ。そうか。ロビンちゃんは、方法がわからないだけなんだね」
今度はサンジ本来の声がして、ロビンは少しだけ残念に思った。
「そうね。わからないだけ」
「けど、わからないだけじゃアイツの気持ちを断る理由にはならない」
言われてロビンはまたも沈黙した。
「方法がわからないだけでアイツを拒むなんて、ロビンちゃんらしくないな」
「どういう意味……」
「おっと、まだ目を開けちゃ駄目だよ。君はまだ見つけていないんだから」
サンジは柔らかい口調で言うと、片手でロビンの顔半分を覆った。急に暗くなった世界に一瞬だけ眉を寄せたが、すぐにサンジが投げかけた言葉を追いかけることに意識を向ける。
「君はゾロに、愛していると言ったんだよね」
「あなた達を愛している、だから特別は作らないと告げたわ」
「アイツは納得しなかったでしょ」
「ええ。諦めないから覚悟しておけ、と」
「それを聞いて、ロビンちゃんはどんな気持ちになったのかな」
「どんな……」
「君の言葉を真に受けないゾロをバカだと思ったのか、話が通じなくて嫌いになりそうとか、話を聞かないから迷子になるんだとか、あの三白眼は恐いから嫌いとか、腹巻きはオッサン臭くてイヤだとか」
「コックさん、論点がずれているわ」
いきなりゾロを茶化しだしたサンジの言葉に、つい笑いがこぼれる。
「剣士さんをあまり悪くいわないで。彼はルフィと同じで、ただ真っ直ぐなだけよ。ルフィと違うのは、彼が一番後ろから私たちを気にかけていることね」
「君の言葉を借りれば、それがアイツの愛し方だ」
男の手のひらがロビンの両手を愛おしそうに包み込む。
「ロビンちゃんだけじゃない。俺たちは皆、互いに愛し合っているんだよ」
サンジはロビンの顔にかかった黒髪を指先で梳きつつ、彼女の耳元へ口寄せた。
「ゾロはね、君のことを愛しているだけじゃ足りなくなっただけさ」
「……今は足りなくても、いずれ余るときがくるものよ」
「気持ちは移ろうもの、だからかい」
「その通りよ。私のせいで、船の空気が乱れるのは嫌なの。私に、特別はいらない」
サンジが少し、意地悪な笑い声を上げた。
「随分と自分に自惚れているね。おまけに君は、アイツを軽く見過ぎている」
眉を顰めたロビンを手のひらで感じ取りながら、彼女の揃った前髪の縁を見つめ、サンジは続けた。
「ロビンちゃんの今の言葉こそ、いらないものだ」
サンジは語気を強めた。
「俺たちの間に、特別なんてものはない。さっきも言ったろう。アイツが君を嫌いになったら、その時にビンタでもクラッチでも、山のようにかけたらいい」
「彼を傷つけたくないの」
「ロビンちゃんが今しているのは、アイツを傷つけていないとでもいうつもりかい」
「私なんか」
「ロビンちゃん、俺まで怒らせないでくれ」
サンジの、本気の怒り声を聞いてロビンの身が竦んだ。いつか海列車で見た顔が脳裏をよぎり、彼女の胸を締め付ける。
「いいかいロビンちゃん、自分を卑下しちゃいけないよ。それだけはしちゃいけない。君はもっと欲張りになっていいんだ」
「私にはもう充分すぎるぐらいだわ」
「違うね。君は今、当たり前のラインに立ったばかりだ」
──なにもかもが初めてだった大きな友人を思い出して、ロビンは俯いた。
「手放せば二度と戻らないものなら、最初から持たないほうがいいわ」
サンジはおかしいとばかりに笑った。彼の声を聞いて戸惑うロビンの髪を優しくなでつける。
「二度とないなんて、どうして言い切れるのさ。人の心は移ろうものなのに」
「それは」
「ロビンちゃん」
サンジは再び真面目な声で彼女に向き合った。
「欲しいものには手を伸ばす、手が届かないなら追いかける。それは、特別なんてことじゃない。やり方がわからないなら教えるよ」
「やり方なんて」
「ロビンちゃん、嘘はつかないで。君は、君を好きだと言ってきたゾロが好きかい」
こくりと息をのんで、ロビンは答えた。
「……好き、よ。たぶん」
曖昧な彼女の答えに、サンジは苦笑いを浮かべたが、それは一瞬のことだった。
「なら、答えは簡単だ。そうだな……お決まりの台詞で、アイツとはじめてみたらどうかな」
「例えば、どんな」
「お友達からはじめましょう──って」
意外な言葉に、ロビンは虚を突かれた。
「私たち、仲間なのに」
「だからさ。友達から関係を発展させるには、お互い駆け引きと歩み寄りが必要だろう」
自分の提案が面白く思えたのか、サンジの声が弾んでいる。
だがロビンは首を傾げた。
「知らない他人から始めるわけじゃなし、そんなことをすれば、彼のほうが困るのではないかしら」
知らず知らず、前向きな発言をしているロビンに、サンジはあと一押しだとふんだ。
「ロビンちゃんはゾロが好きなんでしょ。なら簡単だよ」
「でも今更、はじめましてだなんて」
「そうかな。なら、恋人として、はじめるかい」
サンジの声は茶化しているようで、真剣だ。
「それは……今まで、私たちは、ごく普通の仲間だったのよ」
「ただの仲間でいたゾロが、君にとってより特別になるのが不安かい」
ロビンが頷く。
「彼の気持ちを、私は今日、はじめて知ったのよ」
「恋はいつでもハリケーン。予定を立てて始まるものじゃないよ」
ロビンの瞼が震えている。
「彼の気持ちが真っ直ぐで、私には強すぎるの……」
「そいつは──アイツに繊細さを求めるのは酷ってもんだよ」
諦めてくれと言わんばかりのサンジに、ロビンも否定する気は起きない。
ロビンはもう一度だけ、ゾロとサンジが自分に触れてきた感覚を思い出してみた。
サンジになくて、ゾロにあったもの──それはたぶん、彼がロビンを想う熱い気持ち。
「ロビンちゃん、アイツの気持ちと向き合う気になったかい」
うかがうようなサンジの言葉に、ロビンは姿勢を正して顔を上げた。
「上手くいかなくても、いいのね?」
「もちろん。ただし、これだけは約束してくれるかな──今みたいに、後ろ向きな気持ちでゾロと付き合わないこと」
「難しいわ。私はまだ彼に対して、対等と呼べる程の気持ちがないもの」
「気負う必要はない。俺の気持ちに逃げずにただ向き合ってくれればいい。俺も、構えられるのは本意じゃねぇ」
紛うことのない、ゾロの声が聞こえた。
とっさに見開いたロビンの瞳に、渋い顔をしたゾロが飛び込んでくる。
そのロビンの頬に指の背を滑らせながら、ゾロは彼女の右側に視線を向けていた。
「おい、コック。いい加減にロビンの側から離れろ」
「お前ね、礼の一つも言えないのかよ」
「恩にきる。……離れろ」
「そんなに独占欲の強いヤツとは思わなかったぜ」
苦笑いと共に、サンジはロビンからその身を離した。
08
盲目の釣瓶火
08
事態を把握しきれていないロビンの横で、サンジはゾロと話を進めていく。
「ナミさんどころか俺の手まで煩わせやがって、この借りは大きいからな」
「分かったから、とっとと船へ帰れ、エロコック」
「俄然、強気になっちまいやがって、ムカつく野郎だな。ロビンちゃんにその気がなけりゃ、今すぐテメェを蹴り飛ばしてやるのに」
カップの中身をひと息に空けて、サンジは荷物を手にした。呆然としているロビンの頬をするりとひと撫でする。
途端ゾロから殺気にも似た気が放たれ、真正面にいたロビンの肩が跳ねた。彼女の仕草に、ゾロは慌てて気を静めたが、サンジを睨みつけるのは止めない。
「悪ぃ」
「ククッ……お前、今からそんなんじゃロビンちゃんの身が持たねえぞ。仲間にそれをするのは止めるんだな」
「テメェが悪い。消えろ、クソコック」
サンジは荷物を持ち直し、煙草を揺らした。口調から楽しんでいる気がありありと感じとれて、ゾロは些か尻がむずがゆい思いになる。
「へぇへぇ。お邪魔虫は退散しますよ。一応、晩飯は用意しておくが、宿を取るんなら誰か使いを寄越すか、でなきゃロビンちゃんにお願いしろ。いいな」
「わかった」
サンジの隻眼が頷いたゾロを推し量るように見ていたのは瞬き数回程度の間だろうか。だがゾロには数倍の時間に感じられた。
──ルフィ以外の仲間に試されるなんてな。
サンジとは普段、談笑するよりも喧嘩紛いの戯れが多いが、決して仲が悪いというわけではない。数少ない仲間うちで年が同年齢という気安さがかえって照れくささを生むのだと、そんなことを教えてくれたのがサンジだ。
負けず嫌いな性格も似て、近いだけに素直になれない──。
ゾロとサンジは互いにそれを肌で感じていた。だからこそ馴れ合いのない、腹を割った話が出来るのだろう。
「じゃあね、ロビンちゃん。君の買い物に付き合えなくてごめんね」
「コックさん」
「代わりの荷物持ちに、そっちの筋肉ダルマを置いていくから好きに使うといいよ。どうせ君しか見ていないから、迷子になることもないだろうしね」
サンジはにこりと笑って、新たにくわえた煙草を上下に揺らした。
「大丈夫。君が自分の気持ちを偽らなければきっと上手くいくから。コイツはこの通り、君にメロメロだから」
「テメェもう黙れ」
歯をむいて悪態をつくゾロへ舌を出して答えたサンジは、テーブルの上に手を滑らせ伝票を取ると、その手を二人に振って席を離れる。
「おい、コック」
「今回は俺が持ってやる。ナミさんへの報告はテメェでやれよ」
振り返ることなく、サンジはあっさりと店を後にしていった。
テーブルに残された二人は、しばし語るでもなくまるで互いの出方を探るかのように、固い姿勢のまま椅子に腰掛けていた。
「さっきの言葉、本気だからな」
カップを包み込むロビンの両手が交互に重ね合わさる様を黙って見ていたゾロが、ぼそりと呟く。
ロビンは視線をカップの内側で揺れる水面から、ゾロの傍らに立てかけられた三刀に移し、じっと見つめた。
何となくだが、ゾロと視線を合わせられないでいる。
ロビンは自分の不可解な感情に適切な言葉を当てられず、もどかしい思いに駆られていた。
サンジに計られたとはいえ、不思議と彼を攻める気にはならない。目を瞑ろうと決めた自分の気持ちを、ああもあっさりと暴かれては、潔く白旗を揚げるしかないような気さえしてくる。
──なぜかしら。
ロビンは、僅か半日足らずでゾロに対して特別な感情を抱き始めている自身の変化に戸惑いを隠せずにいた。
「それ、飲んじまえよ」
「え、なあに?」
ゾロの声が近すぎたのにロビンは驚いて、彼の顔をようやく視界に入れた。
ゾロが苦笑いを浮かべて頬杖をついている。
「やっとこっちを向いたな。コーヒー冷めているんじゃねえか。不味くならないうちに飲んじまえよ」
言われてロビンは、カップの中身を飲み干していなかったことに気がついた。
見られながら、カップに口をつける。それが少し気恥ずかしい。
すっかり冷めてしまったコーヒーは、秋島の空気に馴染んで、ロビンの喉から熱を奪いつつ滑り落ちていった。
ゾロは、白い喉が嚥下に動くのを無言で追いかけた。無防備に晒されたそこへ触れたい衝動に駆られて、知らず奥歯を噛みしめる。
ロビンがアーモンド・ラテを飲み干し、カップの縁に付いた紅を指で拭うまでの間、ゾロは彼女から視線を外せなかった。
睫を微かに震わせて、ロビンはゾロと視線を合わせる。
「剣士さん。貴方、これからの予定は」
「お前の荷物持ちだ」
「即答なのね。コックさんの言葉を真に受けなくてもいいのよ」
困ったように笑いかける。
揺れ動くロビンの瞳を離さず、ゾロは腕を伸ばして彼女の柔らかな頬を軽く摘んだ。
「お前は、一々気にかけすぎだ。俺は自分のしたいことしかやらねぇよ」
ふにふにと、からかう仕草で動く指を押さえて、ロビンは眉尻を下げた。
「剣士さん、どうしたの? 今まで、こんな風に触れたことなかったのに」
困惑しているロビンに、ゾロはただの笑みで答えると、押さえつけている白魚の指を捕らえ返し、手元に引き寄せた。爪先に口付ける。
「言ったろう。したいからするんだ。なあ、昼間にサニー号の上でも思ったんだが……ロビン、お前ってナミより可愛いいのな」
左耳の三連ピアスをしゃらりと鳴らしての悪童めいた表情。僅かな上目づかいで指の持ち主を瞳に写す。そこには、
「剣士さ、んっ」
紅玉に染まったロビンがいた。
09
盲目の釣瓶火
09
街中に溢れる喧騒が、くぐもった手触りでじわりと纏わりついてくるのを、ゾロは首をこきりと鳴らして追い払った。
斜めに傾いだ陽光が、舞い踊る埃を照らし雲母の如く煌めかせている。
厚い木肌で誂えた本棚は年季を感じさせるどっしりとした佇まいでそびえており、訪れた者に迷路の入口を思い起こさせた。
ここへきてから1時間は経っただろうか。
ロビンが店のドアをくぐりながら、
「街の中でも由緒ある古書店の一つなのだそうよ」
と、微かに弾む声音で、瞳の中に喜色を滲ませながら話していたのを思い出す。
ゾロは店のレジカウンター脇につけられた小さなテーブルにもたれながら、およそ店の雰囲気にそぐわない大ぶりの湯のみを手にして冷めた緑茶を啜った。
視線は本棚の隙間に注がれたままだ。
ゾロの想い人はカビとホコリとインキの臭いが溢れる中に入り込んでしまい、一向に出てくる気配がない。
曇りガラス越しの淡い光に浮かび上がる白い背中が、一本の白樺を彷彿とさせた。
書物を探す横顔に、アラバスタでビビが仲間達に見せてくれた、古代神話の女神像が重なる。戯れのように不意に浮かんだ幻影を、軽く頭を振うことで追い払う。そうしてロビンの細く長い指が滑るように本の背をなぞるのを見るともなしに見た。
白魚の手が躊躇いがちに羊皮紙やパピルス、竹簡、楮紙の面に触れては離れていく。
——愛おしく、焦がれるように。
情欲にも見て取れる仕草に軽い悋気を抱いた己が胸中に気づいて、ゾロの口からため息が出た。
その吐息が届いたのか、ロビンの肩が小さく跳ねた。と思えば、慌ててゾロへと振り返る。
突然のことにゾロも驚いたが、悟られぬように湯のみを傾け、顔を隠すことで誤魔化した。半分隠した視界から彼女の様子をうかがう。
ロビンはしばし視線をさ迷わせていたが、胸元の本をきつく抱きしめて、足早に本棚の森から出てきた。
まっすぐレジへ進む。
カウンターに置かれた本は革の表紙が色褪せててはいるが艶がかったものばかりだ。色合いが不自然に見えるのは、修復の手が加えられているのだろう。
ロビンは本の最後を開いて栞状の紙切れに顔を近づけては何やら呟く。かと思えば、視線を宙へと向けて難しい顔をしてみせる。
くるくると表情を変えるロビンに、ゾロは新鮮な驚きを覚え、声をかけるのも忘れてつい見入ってしまった。
やがて彼女は頬をやや紅潮させながら、肩に背負った小さなリュックから財布を取り出した。
「こちらをいただけるかしら」
静かな店内を気にして発せられた声は、僅かにかたいが弾んでいる。
「全部ですかな?」
老店主が嗄れた声でたずねた。半分だけ縁取られた眼鏡の向こう側からロビンを見る瞳は、彼女を値踏みしているかのようだ。
「ええ、全て」
「左様でございますか。お客様は目利きでいらっしゃる。差し支えなければ、お見せしたい本があるのですが、ご覧になられてはみませんかな」
ロビンが息を呑んだのがゾロにもわかった。
「お店の主に認められたのはとても嬉しいけれど、手持ちはこちらの本の代金分しか持ち合わせていないの。お勧めされても買えないわ」
店主はロビンの返事に目元を皺だらけにして笑った。
「なに、無粋な動機はごさいませんよ。お客様は特に古い本が好きだとお見受けしたまでのこと。お買い求めになるこちらの本とは毛色が違いますので、無理にとは申しませんが」
「ありがとう。でも……」
「いいじゃねぇか。見せてもらえよ」
思いもよらぬところから出された声に、ロビンは大きく目を見開いた。
ゾロが肩を揺らして吹き出す。
「くくっ。お前、なんて顔してんだよ。豆鉄砲くらった鳩みてぇ」
「だって、あなたがそんなこと言うなんて」
「お前がへんな遠慮をするからだ。おっさんがタダで見せてくれるってんだ、素直に乗っかりゃあいいじゃねぇか」
「でも」
「なんだよ、別に買わせようってんじゃないんだろう」
「あなた、退屈しているのではなくて」
ゾロはテーブルの隅に置かれた急須に伸ばしかけていた手を、ゆっくりと自分の顔へと引き戻した。その手で軽く額を叩く。
堪らないとばかりに小さく声を上げて笑い出した。
「ははははっ。もしかしてお前、俺に気を使って慌てて出てきたのか」
「いけないかしら」
あまりな物言いに、ロビンの気分が急降下する。
ゾロはわかりやすく不機嫌を露わにしたロビンに再び笑いがこぼれてしまった。
「拗ねるなよ。馬鹿にしたわけじゃねえから」
「とてもそうは見えないわ」
声の調子は変わらないものの、ぐっと曲げられた赤い唇に気づいて、ゾロはそこでようやくロビンの沸点が、意外と低いことを思い出した。
「悪ぃわりぃ、お前の拗ねる顔が珍しかったんだ。悪意はないから勘弁してくれよ」
彼女の機嫌を損ねすぎてはかなわない、と少し慌てながら肩をすくめて謝る。
同時に、その一部始終を端で見ていた老店主が、口元を抑え肩先を振るわせる姿に気付いて、二人は揃ってばつの悪い笑みを浮かべて顔を見合わせた。